
- 日時:2022年2月6日(日)15:00-19:20
- 会場:目黒区烏森住区センター食堂
- 1000円+投げ銭(軽食あり)
- 演目: 「運命の卵」「銀河鉄道裏ダイヤ」「風土と存在」、他
- 出演:アンジー、吉水恭子、高野竜、青木祥子、ひなた、小坂亜矢子
--------------
本来なら平原演劇祭#解体ソ連ナイトは、昨年12月26日に開催されるはずだったのだが、開催直前に主宰の高野竜が崖から転落し大けがを負ったため、日程延期で本日開催となった。会場は中目黒駅から15分ほど歩いた住宅街のなかにある目黒区烏森住区センター。この住民センターは目黒区居住者・在勤者でなくても利用できるそうだ。

この会場の食堂(調理が可能になっている)では、平原演劇祭は、2017年にソビエト100年記念#亡命ロシアナイト、2019年に#歳末ロシアナイトの公演を行っている。いずれも食事付き公演だった。今回も食事付き公演だった。
昨年末にこの企画を実施する予定だったのは、2021年12月25日がソ連崩壊の30周年だったからだった。と主宰の高野竜が言っていたのでググってみると、ソ連解体は1991年12月25日だった。しかし私の目にする範囲では、ソ連解体30周年で回顧的な催しや特別番組は日本では特に行われなかったようだ。2017年に平原演劇祭でロシア革命100年記念企画をこの目黒区烏森住区センター食堂でやったときも、少なくとも私の目にする範囲内では、平原演劇祭以外で革命100年にまつわるイベントは行われていなかった。2017年の平原演劇祭#亡命ロシアナイトは、私が参加した平原演劇祭のなかでももっとも印象深いものの一つだったのだが、観客は私を含め4名しかいなかった。
今回は高野竜の転落事故後のダメージで告知がしっかりできていなかったり、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が劇的に広がっていたりしている状況なので、観客数が少ないかと思えば、出演者と合わせ14名の参加者があった。そのうち出演者が6名、主宰の高野竜の配偶者1名なので、純粋観客は7名いたということになる。
プログラムは以下の通り。「#解体ソ連ナイト」というタイトルが示すように、1991年のソ連崩壊に何らかの関わりのある演目が並ぶ。最初の演目の「お茶」は高野が参席者にロシア風の紅茶を振る舞うというもの。


「お茶」の配膳が終わると、小坂亜矢子の「討入」。ピアニカ演奏と歌唱で、山田耕筰のロシア語歌曲(?)ともう一曲ロシア語の歌の演奏があった。曲名はわからない。小坂はピアニカを吹くときはマスクを取り、歌を歌うときにはマスクを付ける。カーキ色のシャツがちょっとソビエトっぽい。
ソ連っぽい気分が盛り上がる。
平原演劇祭2022第3部#解体ソ連ナイト、始まった。お茶のあと、小坂さんの「討入」。山田耕作のロシア歌曲ともう一曲。続いて「ウクライナ」高野竜のソロ。 pic.twitter.com/zFof9lhZdS
— 片山 幹生 (@camin) 2022年2月6日

次の演目「ウクライナ」は、高野竜によるソ連崩壊後のウクライナ情勢についてのレクリャーだった。転落事故の後遺症で、高野の動きはヨタヨタ、言葉は詰まり詰まりではあったが、観客および出演者の大半にとってはその地理的な位置も定かでないウクライナの緊迫した状況について、わかりやすく説明していた。この説明を聞いて、平原演劇祭で以前上演されたトランスニストリア戦争を題材とする作品「ねむりながらゆすれ」の背景がようやくわかった。ルーマニアに隣接するモルドバの領域の一部でありながら、モルドバからの独立を主張する未承認国家、トランスニストリア(沿ドニエストル国)は、ソ連崩壊後の現在もなおソビエト連邦の政治体制が継承されている「国家」とのこと。
高野のウクライナ解説のあと、スターリン時代にその著作のほとんどが出版されることがなかったというウクライナ出身の作家、ブルガーコフの風刺小説「運命の卵」の朗読が始まった。読み手はあんじーだ。赤いスカーフを頭にまとった彼女はマトリーショカ人形のように可愛らしかった。

「運命の卵」は、天才動物学者のペルシコフ教授が偶然発見した動物の繁殖能力と成長を驚異的に増強させる光線が、誤って蛇、カエル、ダチョウの卵に浴びせられ、そこから生まれた巨大な蛇、カエル、ダチョウの大群によってモスクワが危機に陥るという荒唐無稽なSF小説だ。岩波文庫版の翻訳で160頁ほどの中編小説だが、朗読では一部を端折って物語の最初から最後までが語られた。それでも50分ほどの時間、朗読されていたと思う。

あんじーの大学後輩の石田大樹氏が描いた10枚のボールペン画とともに作品は、紙芝居のような感じで朗読された。ボールペンで細かく書き込まれた石田のイラストは作品内容に合った素晴らしいものだったし、あんじーも朗読も集中力が最後まで維持され、聴衆の注意をひきつけるものにはなったいたけれど、絵が小さくてよく見えず、あの絵の面白さがパフォーマンスに十分に生かされていなかったのが残念だった。できれば投影するか、あるいは大きく絵を拡大して見せたほうがよかっただろう。
10分ほどの休憩を挟んでひなたと高野竜の二人による「マハチカラ!」が始まった。カスピ海に面する都市、マハチカラは、ロシア連邦に属するダゲスタン共和国の首都だ。「マハチカラ!」は高野竜とひなたの雑談のような趣向の作品だ。「演目」とされていなければ、リアルな雑談、ないし漫談だと思ってしまうような自然な会話のやりとりだた。

マハチカラはカスピ海西岸に面する都市で、ロシア連邦の一つであるダゲスタン共和国の首都だ。この町の名前は私は知らなかった。ダゲスタンはイスラム系住民の国らしい。高野さんが旅行でこの町にやってきて、ぶらぶらと散歩していると「クリニーング」とカタカナで書かれた看板を掲げたクリーニング屋があったとのこと。「なぜ、こんなところにカタカナのクリーニング屋の看板が?」と当然思う。好奇心をかきたてられ、高野さんがこのクリーニング屋に入ると、そこには東アジア系の人がいて、話はソ連侵攻後、旧満州で抑留された日本人移民の話に移る。という具合の話だったように思う。こちらの集中力が欠けていて話の内容はぼんやりとしか覚えていない。するとひなたが、竜さんと一緒に行ったポルトガルのリスボンでも日本人の子孫に会うって話になって、カステラの発祥の店にタクシーで行って、天正遣欧使節のひとりの千々石 ミゲルの墓が見つかって云々という具合に雑談風演劇は続く。特にまとめや落ちがないまま、次の演目、吉水恭子の一人芝居@銀河鉄道裏ダイヤ」が始まった。

吉水恭子は平原演劇祭初登場の俳優で、昨年末に高野さんが行ったtwitter上での出演者募集の呼びかけに応えて、出演することになったということを先ほど確認した。芝居屋風雷紡というユニットで演劇活動をされている方だった。先ほどの高野-ひなこの雑談が、「遠い異郷で生活することになった人々」というテーマを予告するものであったことが、「裏ダイヤ」を見てわかる。「裏ダイヤ」は、『銀河鉄道の夜』を下敷きとしているが、ロシアの西端に移住した日系移民についての物語だった(ように思う。このあたり、少々もうろうとしていた)。「裏ダイヤ」の上演途中、小坂亜矢子の「討入」がねじ込まれる。ここで彼女が歌ったのは旧ソ連国歌(1977年版)とのこと。

「裏ダイヤ」の上演は40分以上あったと思う。吉水恭子は短い準備期間中に長いテクストを暗記して、「食堂室」をユーラシア大陸に見立て一人芝居として演じきった。素晴らしい。ここで2回目の休憩。いや休憩というより#解体ソ連ナイトの目玉プログラムというべきか、この上演中、ずっと圧力鍋で炊かれていた料理を食べる時間となった。

この圧力鍋は上演中もポコポコと音と立てていて、その存在を意識せざるを得なかった。いわば#ソ連解体ナイトの通奏低音ともいえる存在だった。本日供された料理は、中央アジアのカザフスタン・キルギスの料理、《ベシュバルマク》だった。私ははじめて食べる料理だ。


調理法はシンプルで、皮付きの山羊肉を圧力鍋で2時間ほど炊くというもの。味付けは岩塩のみだ。山羊肉は高野氏が埼玉県にあるハラル肉販売店から買ってきたもの。山羊肉というと、羊肉よりさらに臭みが強そうだが、2時間圧力鍋で炊いた山羊肉は意外なほどクセがない。これにパスタを添え、大量のタマネギスライスをかけて食べる。肉は2.5キロ用意したと言うが、20分ほどのうちになくなってしまった。平原演劇祭では時折食事が出るが、ガサガサッと作って、シンプルな味付けで、立ったままさっさと食べるという落ち着かないスタイルながら、毎回美味しい。ただ岩塩だけの味付けで十分美味しかったけれど、できればアリッサ(唐辛子ペースト)みたいな香辛料と食べたいなあとも思った。食事をしているうちに、日は暮れ、14人が山羊肉を食べる食堂室内はちょっと幻想的な雰囲気になる。

山羊肉の《ベシュバルマク》のあとは、最後の演目「風土と存在」が始まった。「風土と存在」は、高野竜が1999年以降書き継いでいる60作以上にのぼる戯曲連作のシリーズタイトルなのだが、今回はそのシリーズタイトルが上演演目タイトルになっている。最初が高野の前説だ。

「風土と存在」の劇の枕として、数年前から高野がtwitter上でバーチャルに行っている「ロシア徒歩横断演劇」の意義と予定について話始める。ロシア徒歩横断演劇は、ロシアの西端にある飛び地領地、カリーニングラード(旧ケーニヒスブルク)からロシアの東端、アメリカとの国境付近まで何回かに分けて高野が徒歩で移動するという壮大な演劇計画だ。実際のところ、高野の身体の衰えぶりを見ると、この徒歩横断演劇が実現するとは思えないのだけれど、高野は綿密な計画を立て、シミュレーションを行い、それをtwitter上にときどき発表している。
記憶が飛んだり,ろれつが回っていなかったり、話があちこちに脱線したりする、よれよれの前説でいったい「風土と存在」という芝居はまともに上演されるのだろうかと不安になる。二番手は青木祥子で、彼女はアムール州知事代行(?)として、アムール州にあるうち捨てられたような小さな村の人口減少の状況について演説を行う。地誌演劇は高野竜特有のジャンルではあるが、ロシアの小さな村について書かれた文献と高野はどのように出会ったのだろう? またなぜ高野が特に劇的とも思えないこの村の過疎の状況に関心を抱いたのか? シベリアにある自分とは縁もゆかりもない小さな村の状況が事細かに報告されるのを、呆然としながらひたすら聞いた。

シベリアの過疎の村についての報告のあとに、どことなくシベリアの民族衣装風(でもないか)のワンピースを着たひなたが登場する。彼女はまずその土地にまつわる歌を歌った。
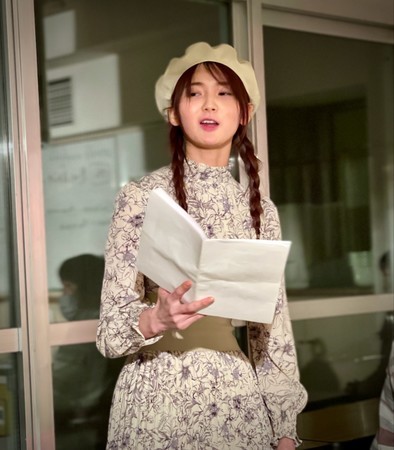
劇を見たのは昨日のことなのに、内容のディテールははっきりと思い出せない。平原演劇祭で上演される高野竜の戯曲は、特に地誌演劇は情報量が膨大で、何回か同じ演目を見た上で、さらに戯曲を読んでようやくある程度その内容が明確になるのが常なのだが。ひなたはこのあたりの民俗学的調査を行う学生のようなことをやっていた。彼女が聞き書きした老女を様子を、ひなたは演じる。老女が語るかつての村の生活は、古代中世に歌われた田園牧歌のようだった。
最後に演じられた「風土と存在」は、高野の語り(かなりヘロヘロ)、青木の語り、そしてひなたの語りの三部構成で、とある村の風土を浮かび上がらせる、思いのほか早大で美しい物語となっていることに、ひなたのパートでようやく気づいた。三人の異なる性質と内容の語りが全部繋がり、私には縁もゆかりもない遠いロシアの小さな村が、幻想的な故郷となった。
終演は午後7時20分頃だった。午後2時開演なので、5時間20分の長丁場だった。昨年の転落事故の後遺症でかなり身体が弱っているらしい高野竜もなんとか最後までもちこえた。

演劇公演における「手作り感」はとても重要で、味わい深いものだと私は思う。区の住民センターの食堂(調理室)で行われた#解体ソ連ナイトは、昔小学校や中学校のクラスでやった「お楽しみ会」を想起させる。素朴な手作りで、洗練はない。しかしだからこそ逆説的に、そこで提示される特別な時空の充実は深まるように私は思う。平原演劇祭にいると、演劇の喜びというのは、作品の面白さや卓越した演技、見事な美術を楽しむよりもむしろ、こんな具合に、日常のただなかに異世界を作り出し、それを他の人たちと共有することにあるのではないか、と思えてくる。
