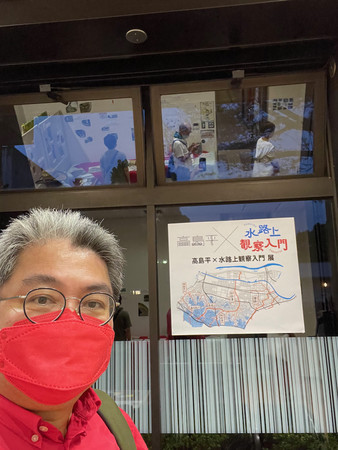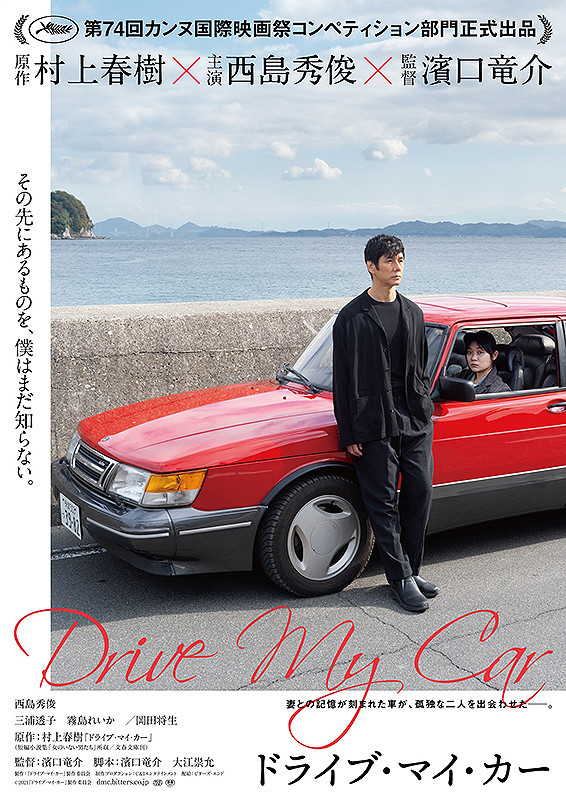note.com

平原演劇祭では田宮虎彦の小説の朗読を月例で行っている。ここ数回、この朗読の会を見に行けてなかったのだが、黒菅藩(くろすげはん)という架空の東北地方の藩を通して、新政府軍に敗北していく幕府側についた武士たちを描く連作集を取りあげているとのこと。
今回は私の最寄り駅の地下鉄赤塚付近でこの「演劇前夜」の朗読をやるということで、私は見に行かないわけにはいかない。ただ私は告知をtwitterで見ただけで、当日何をここでやるのかについては全く予習をしていなかった。田宮虎彦の黒菅藩ものの一つ、「菊の寿命」を読むというのも、朗読が始まってから知ったのだった。

集合は午後1時に東京メトロ、地下鉄赤塚駅の一番出入り口を出たところだった。川越街道をはさんで一番出入り口の斜向かいにある出入り口を私は日常的に利用している。まさに私にとっては地元中の地元である。秋分の日だったが、昨日は真夏の太陽が照りつける暑い日だった。

集合時刻10分前に駅出入り口に行ってみたが、誰もいない。成増側にあるこの一番出入り口は、地味な地下鉄赤塚の出入り口のなかでもっとも利用者が少ない地味な出入り口だ。もしかすると集合場所を間違えたのかと思い、人の乗降が多い池袋側の出入り口まで見にいったけれど、やはり平原演劇祭の観客らしい人はいなかった。もとの場所に戻ると、高野竜さんの妻のみきこさんが出入り口のそばにいた。観客は私ひとりかと思えば、常連のMさんの姿もあった。結局、今日の観客は私とMさんの二人だけだった。
高野さんは1時15分ごろに地下鉄赤塚駅出入り口にやってきた。地下鉄赤塚で奥さんを下ろしたあと、高島平まで車で戻り、そこに車を駐車したあと、赤塚まで歩いてきたらしい。車を高島平に駐車したのは、今回の平原演劇祭の終着点が高島平だからだ。
赤塚と高島平の距離は三キロぐらいだが、かなり急な上り下りがあるうえ、気温が33度の炎天下である。始まる前から高野さんは暑さと疲労でヨレヨレの状態で、地下鉄の改札に下りる階段でうずくまっている。


どんなにボロボロの状態でも演劇をやるのが高野さんだ。しばらくへばっていたが、立ち上がり、川越街道沿いの実に散文的な風景のなかで平原演劇祭は始まった。まず赤塚から北に向かって高島平の向こう側、埼玉県との県境をなす荒川まで流れる前谷津川の川筋を下っていく。といっても五キロほどの長さの前谷津川は全面的に暗渠になっていて、地表を流れていない。赤塚近辺に20年ぐらい住んでいる私は前谷津川の存在を知らなかった。古くからの住民以外は知らないだろう。この前谷津川の水源は川越街道沿いに建つマンションのゴミ置き場の奥にあった。板橋区がちゃんと「ここは水路です」と看板を立ている。しかし水路とは書いてあるものの、その水路にはふたがかぶせられ流れている水は見えない。看板のそばに行くと、ふたの下で水が流れている音が聞こえた。川越街道を越えた向こう側には川筋跡らしい空間は見当たらない。まさにここが前谷津川の水源なのだ。


このあたりは家の近所なので、ちょくちょく通る。たしかに川が流れていた(現在も地下で流れている)ということに気がつけば、暗渠っぽい路地が川越街道沿いのマンションのゴミ集積所から北に向かって続いていることがわかる。

暗渠となっている道の出入り口には、上の写真のような車止めが設置され、車が進入できないようになっていた。一戸建ての住宅が並ぶなか、ぐねぐねと伸びる前谷津川暗渠に沿って歩いて行った。気温が高くて、歩くのはきつかったが、既にバテバテの状態で杖をつきながらゆっくり歩く竜さんがガイドだったので、ついていくことができた。一時間ほど高島平方面に歩いたところで、アイスクリーム休憩を取る。かき氷屋があれば入りたいような感じだったのだが、そんな気の利いた店はこのあたりにはない。ひたする木造モルタルの一戸建て住宅とアパートが乱雑に並ぶ。


《高島平暗渠×水路上観察入門展》@高島平図書館で配布されていたパンフレット。この地図にある「前谷津川」沿いを今回歩いた。
アイスクリームを購入したCOOPは板橋区役所赤塚支所の近くにある。2011年までは板橋区民だったのでここには何回か来たことがある。地下鉄赤塚駅からここまではゆるやかな上りになっているが、この先はかなり急な下り坂になる。この下り坂から、田宮虎彦「菊の寿命」の朗読が始まった。午後一時半ごろに赤塚新町駅を出発して、朗読が始まったのは午後三時すぎだったように思う。



両側を住宅に挟まれた、狭くて急な階段をそろりそろりと用心深く下りながら、高野さんは架空幕末歴史小説「菊の寿命」を朗読した。水まきをしていた下り階段の左手のアパートの住民がいぶかしげに朗読しながら階段を下りていく竜さんを見ていたが、何も言われなかった。危ない人だと思われたのだろう。
坂を下りきると、今度は上りになる。この上り坂も階段でかなり急だ。そして登り切ったところに赤塚植物園があり、高野竜さんは朗読を続けながら植物園に入っていった。


植物園なのでいろいろな植物がある。そして植えられている植物を歌った万葉集の歌を記した標識が立っていた。この植物園を回遊しているときは「菊の寿命」朗読では幕府に仕えてきた黒菅藩の歴代藩主の事績と没年が列挙されている箇所だった。竜さんは時折、植物の標識に記された万葉集の歌も立ち止まって読み上げる。「菊の寿命」は、黒菅藩の藩主、山中和泉守重治の独白なので、傍目からみると頭の可笑しい人が独り言をブツブツつぶやきながら、散歩しているように見えたかもしれない。植物園には小さな子供を連れた親子連れが数組と植物園の植栽を管理する人たちが数人いた。
今回は「虫除け持参」が事前に推奨されていたが、この植物園は蚊がたくさんいた。アイスクリーム休憩のときに、高野さんの奥さんから腕に虫除けスプレーをふきかけてもらっておいてよかった。


赤塚植物園に附属し、その隣にある農園で「菊の寿命」を竜さんは読み終えた。朗読時間は50分ぐらいか。読み終えたのは午後四時半ぐらいだった。幕府軍側で、新政府軍と戦い、悲壮な最期を迎えることになる藩主の話。竜さんは最後は、靴を脱ぎ、上半身裸になっての朗読だった。農園の緑をバックにした朗読は美しく、力強い。農園の閉園時間間際ということもあり、最後のほうは農園には我々4人しかいなかった。



本日の締めは、高島平図書館で行われている《高島平暗渠×水路上観察入門 展》だ。図書館は午後8時まで空いているとのこと。この展示を見ることで、前谷津側暗渠歩きと田宮虎彦「菊の寿命」の朗読のつながりがよりはっきり浮かび上がっているはず、と竜さんは言う。
しかし実のところ、私は田宮虎彦「菊の寿命」をなぜここで朗読したかったのか、その理由がまだわかっていない。
植物園から高島平図書館までは2.5キロぐらいの距離がある。出発時点で既にヘロヘロで、そのあと歩き朗読を続けた高野さんはもちろん、みきこさんや観客二人もかなり疲れていたのだが、暗渠路沿いにぶらぶら高島平まで歩いて行くことにする。


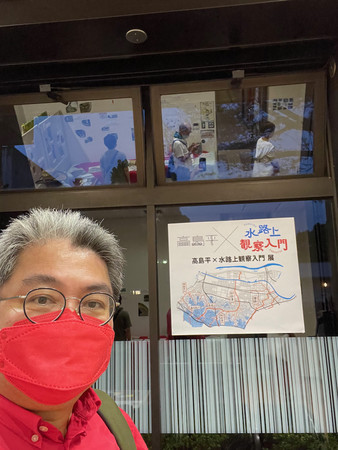
図書館に着く頃にはあたりは暗くなっていた。図書館に入る前に、高野さんが途中で買ってくれたホワイト餃子で腹ごしらえをした。遊歩道のベンチに座って手づかみで、一人二個ずつ食べた。こんな落ち着かない状況で手づかみ餃子なんて気が進まないなと思ったけれど、路上でのホワイト餃子、けっこういける。
図書館に到着したのは午後五時半過ぎだった。《高島平暗渠×水路上観察入門 展》はごく狭いスペースでの展示だったが、企画者のかたが撮影したキャプション入りの写真や昔の新聞記事などのスクラップなどで、今日、私たちが歩いてきた前谷津川の過去と今を振り返ることができるう内容になっていた。
高島平図書館から歩いて6分の別の場所で、《いたばし暗渠×水路上観察入門 展》という関連企画が行われていることを今になって知る。図書館についた時点で疲労でヘロヘロになっていて、しかも時間も午後五時半を過ぎていたので、知っていたとしても足を運ぶ元気があったかどうかわからないが。
解散は高島平図書館で午後六時半。私にとっては近場の遠足演劇だったが、午後一時から六時半、暑い中をだらだらと歩き続けるという長時間体力消耗演劇となってしまった。疲れたけれども、久々に外を歩き回って、気分はいい。